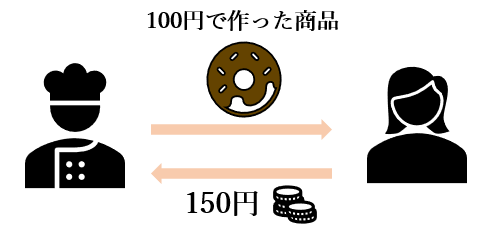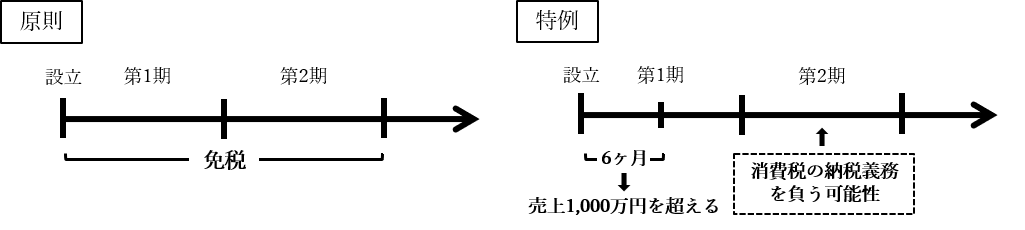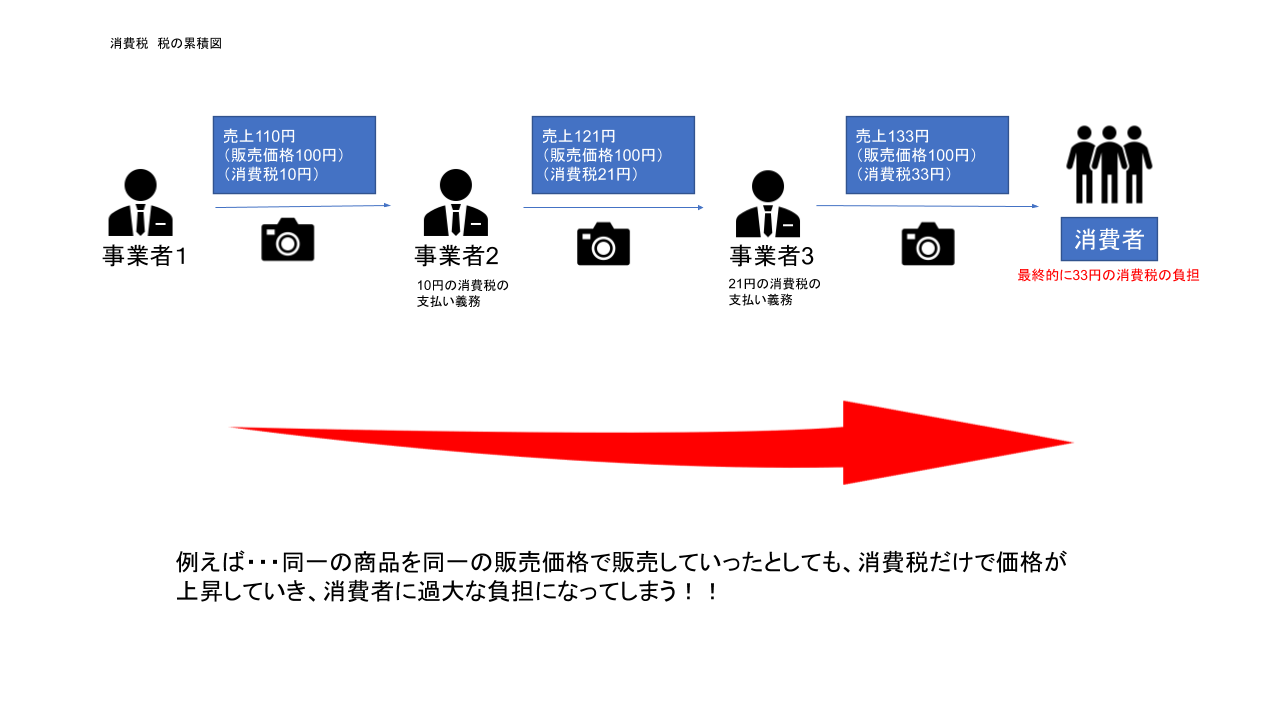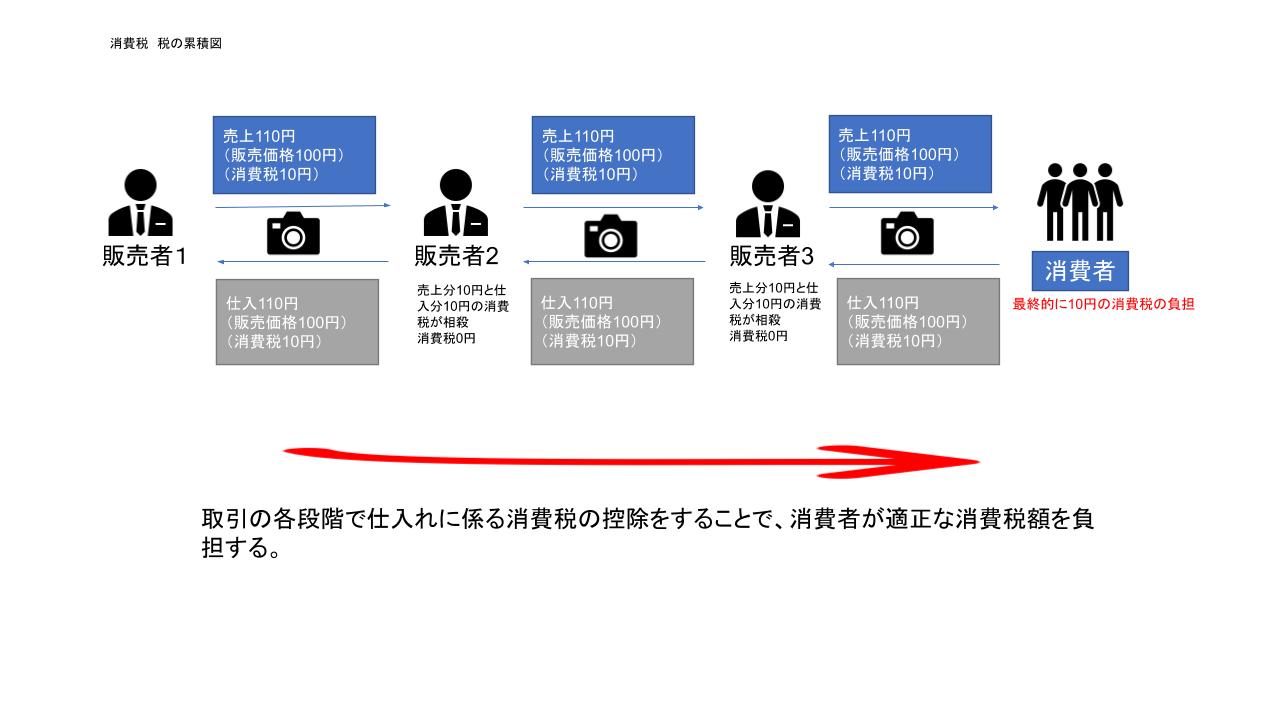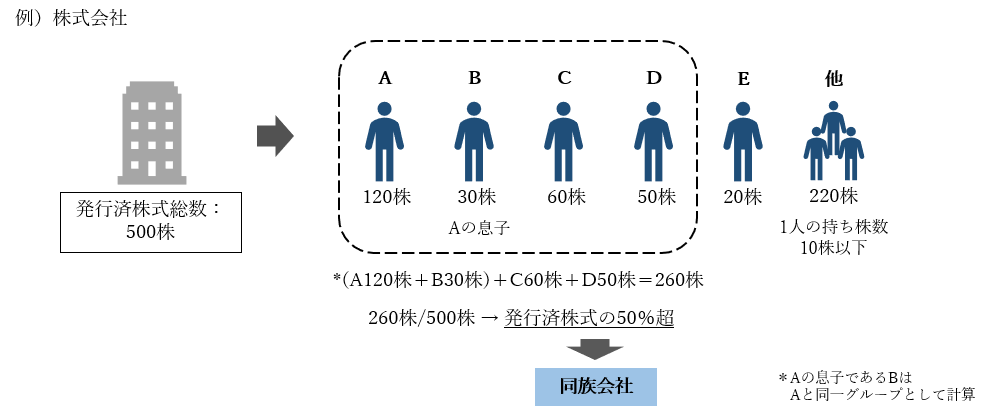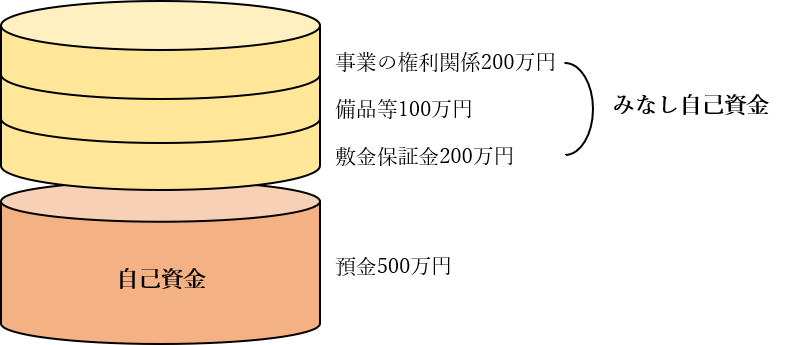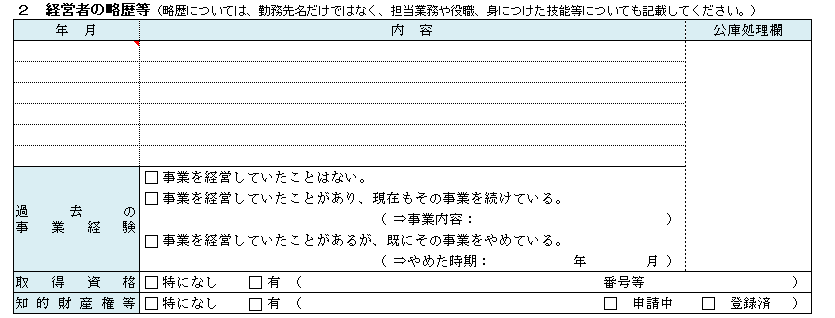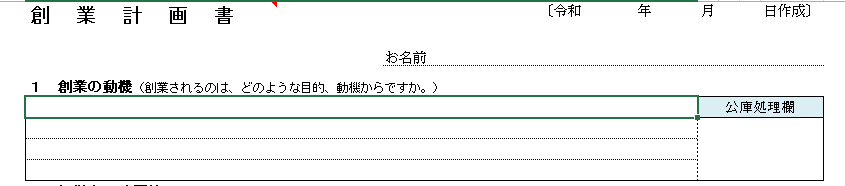起業される方などについて会社の税金について、最初に驚くのは役員報酬ではないかと思います。
「え!!役員報酬って変えられないの!」
そうです。会社の税について定めている法人税法には、役員報酬の変更には非常に厳しい制約があるのです。
その趣旨について簡単にいってしまうと、役員報酬を自由に変更してしまえるような状態ですと、会社の利益を自由に操作して、法人で殆ど税金を払わないなんて状態がおきてしまうこと防ぐ目的があるわけです。
では、まずは役員報酬、つまり役員のお給料が、会社の経費(法人税法上は損金といいます。)として認められるための要件をご説明します。役員報酬については法人税法34条に定められているのですが、税法上の用語を理解していないと読むことができず、かなり難解な条文となっておりますので、中小企業の社長にとって重要と思われる部分を解説していきます。
解説
まず法人税法34条についてまず役員報酬は、金銭の支出による単純なお給料だけではなく、経済的な利益を含むことを理解してください。経済的な利益とは、例えば会社が役員に対しての貸付金を免除した場合だったり、あるいは会社が役員自身の責任で起こした事故の損害賠償金を肩代わりしたりといった時に、役員がうける利益などをいいます。
法人税法34条では、次の3つの要件のすべてをクリアすることで役員報酬を会社の損金(いわゆる経費)とすることを認めています。
① 1項基準
その役員報酬が、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の要件を満たす業績連動給与(これは中小企業にはあまり関係がないので省略します。)であること。法人税法34条1項に定められているため、これをいわゆる1項基準といったりします。
では定期同額給与、事前確定届出給与とは何でしょうか?
①定期同額給与・・・一般的にはその会計期間の開始の日から3ヵ月以内に株主総会により決議されるもので、各支給月における支給額が同額である給与
②事前確定届出給与・・・いわゆる賞与ですが、利益操作につながらないよう支給時期及び支給額を事前に税務署に届出しなければならない。届出書の提出期限は株主総会による決議の日から1か月以内とその会計期間開始の日から4か月以内のいずれか早い日。新たなに設立した法人については設立の日から4か月以内。
つまり毎月のお給料は同額を支給すること、賞与などについては事前に税務署に届出をだすことが求められています。役員には利益還元的な賞与は認められない、ということですね。
ただし主に二つ例外があります。
①臨時改定事由・・・役員の役職の変更などにより定期同額給与を変更する場合。役員報酬の変更をする役員の役職の変更が定款や株主総会決議等により客観的に判断できることが重要です。租税回避が目的であると判断されると認められませんので注意が必要です。
②業績悪化改定事由・・・業績悪化を理由に役員報酬を減額する場合。自分の会社または得意先の会社の業績に悪化が著しく悪化で役員報酬の減額も利害関係者との関係性からやむを得ないような状況です。単に、資金繰りの悪化や、業績目標に達しないなどの理由では認められません。
臨時改定事由又は業績悪化改定事由に該当にすれば、毎月のお給料を変更することも可能ですが、こちらの判定には客観的にその状況を税務署に理解してもらう必要があり、慎重な判断が必要になります。
② 2項基準
その役員報酬が不相当に高額でないこと。法人税法34条2項に定められているため、これをいわゆる2項基準といったりします。
とはいえ、不相当に高額といわれても、どこからが不相当であるかなど曖昧でわからないと思います。
不相当に高額であるか、どうかについては2つの基準があります。
形式基準
形式基準では、株主総会や取締役会等で決定された役員報酬の上限額を超えていないかどうか、で判断されます。役員報酬は一般的には株主総会等の決議に関する議事録に役員報酬について定めるのですが、場合によっては定款などに役員報酬の限度額を定めている場合があるので注意が必要になります。そもそも設定した目的はコンプライアンスとか利害関係者に対する配慮であったりはするのですが、株主総会や定款に定めた限度額を超えていると判断されると、越えた部分は不相当に高額とみなされます。
実質基準
実質基準では、その役員の職務内容や会社の収益、従業員に対する給与の支給状況、類似法人の役員報酬の支給状況等から、支給している役員報酬が不相当に高額となっていないかどうか、で判断されます。 国としては極端な租税回避を防止するための基準ですが、客観的な基準はなく、税務調査時の判断ということになります。
しっかりと売上や利益をあげている会社の役員の役員報酬が高い分にはあまり問題がありません。
問題になりやすいのが、会社が多額の赤字を計上しているのに役員に高額な報酬が支給されている場合や、非常勤の役員(特に親族)に対して役員報酬を支給している場合は、税務調査で勤務などの実態が論点となりやすく、役員報酬が適正であるか、前もって検討しておくことが必要です。
③ 3項基準
事実の隠蔽や仮装するような経理をしていないこと。
法人税法34条3項に定められているため、これをいわゆる3項基準といったりします。
これはごく単純な話で、ウソや事実と異なる理由によって役員報酬を支給している場合には認めません、ということです。
そもそも支給している実態がないお給料などがこれに当てはまります。帳簿の動きだけで支給しているように見せかけても認めません、ということです。
まとめ
役員報酬は3つの要件を満たす必要があることについて説明してきました。
一般的な毎月支給されるお給料については3か月以内には決定した支給額を支給し、いわゆる賞与の場合には届出をした支給額を支給時期に支給しなければなりません。これを守らない場合には、税務調査時にそれが発覚すると、これらの役員報酬が部分的またはすべて否認されることとなります。
さらに、2項基準では不相当に高額ではなく、3項基準では偽りや仮装経理でないことが要件になっています。
役員報酬が否認される場合には、否認された部分の報酬は法人税の課税所得となり利益がでれば否認された部分の法人税を追加で支払わなければなりませんし、すでにお給料として計上している部分の所得税は減額等なく変わりません。法人税法上で役員報酬が制限されていたとしても、実際にお給料が出ているのなら所得税は払わなければいけないわけです。役員報酬が否認されてしまうと、税金上はかなり大きな負担になることがおわかりになると思います。
役員報酬への対策はどうすればいい?
このように厳しい制限のある役員報酬ですが、経営者にとってもっとも厄介なのは事業年度のはじめに決めた金額を動かせないということではないでしょうか?
「今年、1年の成績がどうなるかなんてわからない?」と。
その1年の業績に対して役員報酬が多すぎれば会社には多額の赤字が計上され、金融機関に借入などがある場合には信用が落ちるでしょうし、また役員報酬に課せられる社会保険料、所得税、住民税などの税負担により資金繰りが悪化する可能性があります。とはいえ、その1年の会社の業績に対して、役員報酬が少なすぎれば、会社には多額の法人税が課せらます。その翌期以降は法人税を引かれた後の現金から役員報酬をはらい、ここから社会保険料、所得税、住民税などがひかれていくと、稼いだ現金のうちかなりの金額が税金でひかれてしまうことになりかねません。
こういった事態を少しでも緩和するためには、決算期にはしっかりと過去のデータを照らし合わせて、限られた情報のなかでもしっかりと会社の業績予測をおこなっていくことです。会社の毎月の試算表をしっかりと整理していけば、業績予測や適正な役員報酬の算定のために必ず有用な情報になります。
臨時改定事由又は業績悪化改定事由に該当し、会社の状況に合わせてお給料を変更できたのに見過ごしたため、融資対策や不必要な税負担で会社をさらに窮地に陥らせることもありえます。
またこれに加えて、そもそも役員になる人について税法独自の基準があるので注意が必要です。これを法人税法では、みなし役員といいます。みなし役員についてはこちらの記事をご参照ください。
【特殊!!会社のみなし役員】
会社の税金について定めている法人税法のなかでも難解な条文になっております。判断に迷うような場合には税理士に相談されることをオススメします。